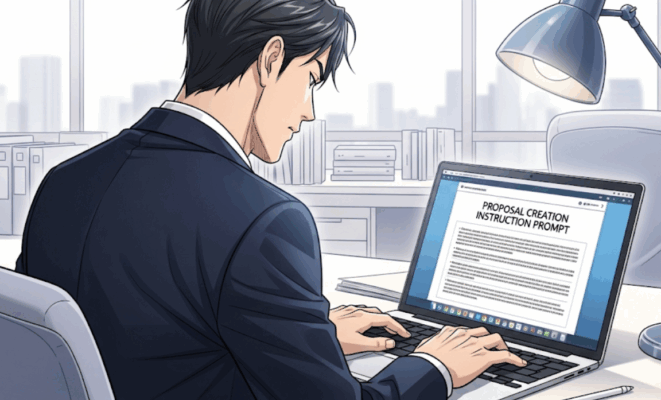
「AIとは、ちょっと頼りになる後輩のつもりで付き合うとちょうどいい」
最近SNSで、こんな投稿を見かけました。この言葉、自分が普段感じていることを、上手に言語化してくれているなと感心しました。
生成AIに何かを頼むとき、何となく“仕事をお願いする感覚”になります。
曖昧に頼めば、それっぽいけどズレたものが返ってくるし、丁寧に頼めば想像以上の成果物が返ってくる。
そう考えると、「後輩や部下に頼むときと同じ」だなと。
そしてこの話、実はもっと深いところで重要な示唆を含んでいるなと思いました。
それは、「AIをうまく使えない人って、部下もうまく使えてないのでは?」ということです。
AIと部下は似ている
AIは、ちゃんと指示を出せば、それなりに良い仕事をしてくれます。
「この資料を、経営者向けに3分で読めるボリュームで、懸念への答えを箇条書きにして要約して」と頼めば、報告資料の叩き台を瞬時につくってくれます。
最初の完成度はともかく、出てきたアウトプットをレビューして、「ここは論拠が弱い」「この構成は順番を変えよう」などとフィードバックを繰り返すと、どんどん精度が上がってきます。最終的には、その領域においては、少し曖昧な指示でも質の高いアウトプットが返ってくるようになります。
このプロセス、部下とのやり取りと極めて近いと思います。
最初は細かく指示が必要だった新人も、フィードバックを繰り返すことで成長し、やがて「あの件、いつもの感じでやっておいて」でちゃんと成果を出してくれるようになる。
AIとの付き合い方は、まさにそれと同じように感じます
指示のスキルが重要
しかし、AIをうまく活用するには、こちら側(指示を出す側)にいくつかのスキルが必要です。
まずひとつは、プロンプトを書く能力です。
たとえば――
・「こういう情報を使って、これこれの視点で資料を作って」
・「この提案資料を、論理性・構成・説得力の観点で評価して」
・「この主張を裏づけるためのデータを、信頼できる出典から探して」
・「役員向けに、現状と課題をパワポ1ページに簡潔にまとめて」
こんなふうに、何をどうしてほしいのかを、こちら側が明確に指示する必要があります。
こちら側の指示が悪ければ、それなりのものしか出てきません。
そしてもう一つは、結果を評価する能力です。
AIが出してきたアウトプットを見て、「この論理は甘い」「データの出典が怪しい」「結論が弱い」などと判断し、次にどう指示すべきかを考える。ここには、それなりの知識と判断力が求められます。自分の能力や知識が不十分だったり、自分の頭の中が整理されていないと、正しく評価できず、折角のアウトプットも意味がなくなってしまいます。
「AIに何をどう頼むべきか、そしてAIが出した結果をどう評価すべきか」が試されているのです。
AIで学ぶ “部下との付き合い方”
そう考えると、AIの活用スキルは、単なる「最新ツールの使用スキル」に留まらないといえます。
それは、「指示を出す」「レビューする」「育てる」といった、マネジメントのスキルそのものかもしれません。
だからこそ、部下に「思った通りのことをしてくれない」「なんでそんなアウトプットになるのか分からない」と感じている人は、ぜひAIとの対話を通じて、自分の指示力を客観的に見直してみてほしいと思います。
AIは、指示が間違っても、曖昧でも文句を言いません。
何度でもやり直しがきくし、修正指示を出せば、ちゃんと学んで次に活かしてくれます。
これは、練習相手としては最高です。
「部下を使えない人はAIも使えない」――
逆に言えば、「AIを使いこなせるようになれば、部下もうまく使えるようになる」。
そんな視点で、まずはAIを“育てる”つもりで接してみてはいかがでしょうか。
(とはいえ、プロンプトが書けてしまえば、部下に頼むこと自体が不要、という未来がすぐそこに来ている気がしますが。。。)
