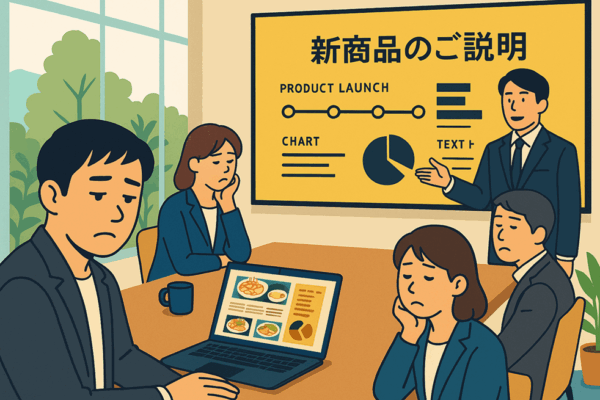
「部長、今日のお客さん、途中で寝ていましたよね?」
商談の帰り道、営業担当が苦笑いしながらつぶやきました。
部長も肩をすくめます。
「質問もほとんどなかったよね。」
がんばって作ったのに。
がんばって説明したのに。
それでも“刺さらない”。
なぜか?
私自身も、プレゼンする側、される側で、こんな状況に何度も出会いました。
つまらないプレゼンには 共通要素があります。
しかも、やっている本人ほど気づかない。
今回は、その 「退屈なプレゼン」の特徴を紹介します。
読むと、「そりゃ退屈になるわ…」と納得していただけるはずです。
1. 情報てんこ盛り
まずは鉄板。
とにかく盛る。
言いたいことをとにかく詰め込む。
スペック、機能、沿革、実績、図表…。
“全部伝えよう”とするほど、相手の脳は処理不能になります。
実際、人が初見で理解できるのはせいぜい3つ。
それ以上はノイズになります。
ある方は言いました。
「スライド10枚目で、夕飯のこと考えてたよ。」
理解されても、記憶には残らない。
盛れば盛るほど無風になる。それが現実です。
2. 抽象的・概念的・教科書的
退屈を倍増させる方法がこれです。
「DXが重要です」
「価値創造が必要です」
「標準化がポイントです」
「今の時代、CRとCPAです」
正しいけれど、まったく面白くない。
理由は単純で、抽象的な話しは
・自分に関係あるかわからない
・映像でイメージできない
・だから、脳の負荷が高い
からです。
イメージできないものは理解できません。
理解できないものは面白くありません。
教科書がつまらないのも、同じ構造です。
3. 課題への“仮説ゼロ”
つまらなさを一段と加速させるのが、
「仮説ゼロ」という特徴 です。
抽象的な説明のあとに、こう続くパターンがあります。
「御社ではどんな課題がありますか?」
「どんなことでお困りですか?」
これ、丁寧そうに見えて、実はもっとも雑です。
お客さんの脳内ではこう翻訳されます。
・うちのこと調べてない
・ 熱意を感じない
・自分たちに興味がない
・どこの会社にも同じ話をしているんだろう
つまり、「このプレゼンは自分ごとではない」と判断するのです。
逆に、仮説があるだけで空気が変わります。
「公表されている情報を踏まえると、おそらく御社では、
営業の効率がボトルネックだと思いました。」
「原因は、御社のケースでは、XXXが大きいのではないでしょうか。」
「だとすると、こういう解決方法が、効果が高いと考えます。」
お客さんの心の声はこうです。
「お、うちのこと見てるな。」
ここに触れないプレゼンは、どれだけ丁寧でも
上っ面的に聞こえます。
4. 良いことばかり
メリットだけ並べる。
不都合は一切触れない。
リスクも言わない。
しかし人間は本能的に
良いことしか言わない人を信用しません。
詐欺の勧誘のようなプレゼン
自慢話満載のプレゼン
訊きたい人はあまりいなしでしょう。
意思決定とは、メリットとリスクを比較して行うものです。
良いことばかりのプレゼンは逆効果です。
5. 物語の欠如(No Surprise)
説明はある。
ロジックもある。
図も多い。
でも、心が動かない。
理由はシンプルです。
人は 驚き・意外性・変化の瞬間 が好きだからです。
NHKの「プロジェクトX」が面白いのは、
人・状況・葛藤・突破があるからです。
つまり、物語がないプレゼンは、退屈が必然と言えるでしょう。
自分勝手を避け、相手を動かす
上にあげたプレゼンの特徴を総称すると、
「自分勝手なプレゼン」と呼ぶことができます。
「サプライヤーロジック」とも。
つまり、相手不在の供給者目線ということです。
どれも「やってしまいがち」ですが、
すべてが人間の脳の動きに逆らっています。
だからつまらないのです。
逆に言えば、
この5つを外すだけで、同じ資料でも別物になります。
プレゼンは技術より設計。
「つまらないプレゼンの作り方」を知ることは、
「面白くて刺さるプレゼン」への一番の近道です。
「スモールビジネス」立ち上げ支援コンサルティングを提供しています。
お問い合わせください。
Facebookをフォローする👇
