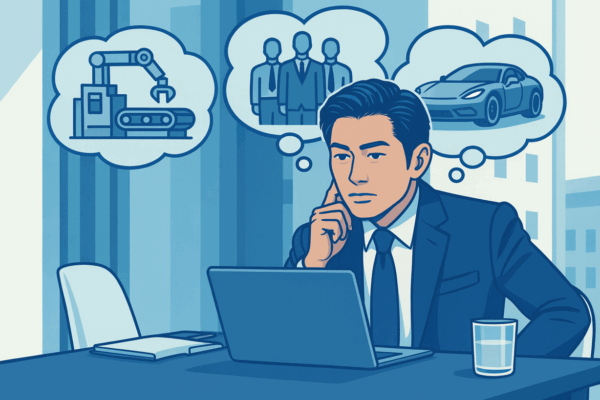
「節税になるんで外車を買ったんですよ」
「やっぱり経営者はオフィスが立派じゃないと格好がつかないので」
「有名な経営者が通うラウンジの会員になりました。勉強代だと思えば安いものです」
中小企業の経営者と話していると、こんなフレーズを耳にすることがあります。
気持ちは分かります。良い車に乗れば気分は上がりますし、きれいなオフィスは社員の士気を高めます。ラウンジ会員になれば有名な経営者など刺激的な出会いがあるかもしれない。
しかし、「それって投資というより無駄遣いでは?」と疑問に感じることもあります。
今回は、この 投資と無駄遣いの境界 について考えてみたいと思います。
(*尚、本稿では、資本的支出、経費的支出を合わせて、「投資」とします。)
投資とは?
投資とは一言で言えば 「将来の事業成長のための支出」です。
たとえば、
・新しい設備を入れて、生産量を拡大する
・ITシステムを導入し、業務の効率化を図る
・人材育成のために、外部の研修プログラムに社員を派遣する
これらは短期的にはお金が出ていきますが、将来的に利益成長を生むことを目的としています。だから投資と呼ばれるわけです。
無駄遣いとは?
では無駄遣いは何でしょうか。こちらも例を挙げてみます。
・分不相応に豪華なオフィスに入居する
・ほとんど使われないクラウドサービスに毎月課金する
・月に数回しか乗らないのに営業車を購入する
・仕事の見込みがないのに人を雇ってしまう
共通しているのは 「収益につながる見込みが見えない支出」 という点です。
自分の気持ちや見栄を満たすことはあっても、ビジネス的な回収の道筋が見えていません。
境界はどこに?
「そうはいっても、その境界が難しいんだよ」と思う方もいるでしょう。
実際に投資と無駄遣いの境界はとても曖昧です。ここでいくつか事例を見てみましょう。
1. 成功者の真似をする
「成功したければ成功者と付き合え」という考え方があります。成功者の思考回路や金銭感覚は、一般人と違うのは確かでしょう。同じように高級車に乗り、同じように高い店に出入りすることから学べることも沢山あるでしょう。しかし、その出費が本業の成長にどう結びつくのでしょうか? その道筋がなく、単にキャッシュを減らし、将来の投資資金を奪ってしまうのであれば、これは無駄遣いに分類されるのではないでしょうか。
一方で、成功者の習慣や思考を真似ることは有効です。たとえば、朝のルーティンや読書習慣、時間の使い方。これらはほとんどコストがかからず、大きなリターンをもたらします。このように「形」ではなく「仕組みや習慣」を真似るなら、投資と言えるでしょう。
2. 多店舗展開
飲食や小売では「出店してこそ一人前」という空気があり、赤字の1号店を抱えたまま勢いで2号店を出す経営者もいます。けれどもこれは典型的な無駄遣いです。型ができていないまま拡大しても、失敗の再生産にしかなりません。
逆に、1号店で利益モデルが確立し、オペレーションもマニュアル化されていれば、2号店は投資になります。再現性のあるモデルを広げることは、経営をスケールさせる正攻法です。
3. 人材採用
「とりあえず不安だから」「いい人がいたから」という理由で人を雇うケースもあります。しかし、仕事の見込みがないのであれば、人件費だけが積み上がり、固定費として経営を圧迫します。その人の稼働のために、収益性の低い仕事を無理やり作る。これでは本末転倒です。
一方で、将来の案件や成長戦略が見えていて、人材確保がボトルネックになっているならどうでしょう。優秀な人材を先行的に確保し、育てておくのは投資です。むしろタイミングを逃せば、後で取り返しがつかないこともあります。
判断基準は「収益化の見込み」
結局のところ、投資と無駄遣いを分ける基準は 「将来の収益化が見込めるか」 です。
もちろん見込みはあくまで仮説です。外れることもあるでしょう。
しかし、シナリオすら描けない支出は、もはや投資ではなくギャンブルです。
「たまたまうまくいった」ことはあっても、ビジネスとしては成立しているとは言えません。
投資なら何でも良いのか?
では、収益化の見込みがあれば何でも投資として正当化できるのでしょうか。
実はそう単純ではありません。見込みはあくまでも見込みであり、経営には常にリスクが伴います。投資を考える前に、リスクヘッジも合わせて考えておくべきでしょう。
リスクを軽減するために重要なのは、次の二つです。
1. 損益分岐点を下げること
2. キャッシュに余裕を持つこと
損益分岐点を下げる
損益分岐点とは、売上と費用がちょうど釣り合う水準のことです。
固定費が高ければ高いほど、このラインは上がり、黒字化が難しくなります。
・リモートワークやシェアオフィスを利用し、可能な限りオフィス家賃を下げる
・固定給の正社員ではなく、変動給の外注やパートを活用する
・営業車やオフィス機器などは、リースやレンタルを活用し、変動費化を図る
投資を検討する際には、こうした工夫で固定費を下げれば、必要な売上高も下がり、経営はぐっと楽になります。
キャッシュに余裕を持つ
「毎月ギリギリの資金繰り」「赤字が続く」「借金での自転車操業」という状況では、経営者も社員も不安でしょう。
資金に余裕のない不安定な経営は、思い切った戦略判断を妨げ、選択肢をどんどん狭めてしまいます。
だからこそ、キャッシュの余裕を勘案した投資をすることが重要です。
収益化のシナリオ
ここで少し立ち止まって、自社の支出を振り返ってみてください。
・「これは投資だ」と思っている支出、本当に将来の収益につながるでしょうか?
・ あるいは、自己正当化の言葉で無理やり納得させていませんか?
「これはブランディング投資だから」「勉強代だから」というフレーズは便利ですが、実は、収益化のシナリオがないケースも多いものです。
投資と無駄遣いの境界線は曖昧ですが、判断基準はシンプルです。
・将来の収益化のシナリオに沿っているか。
・損益分岐点を下げ、キャッシュに余裕を持ちながら実行できるかどうか。
この二つを満たしていれば、投資は「成長のための一歩」になります。
一方で、根拠のない支出は「自己正当化された無駄遣い」にすぎません。
経営は常に選択の連続です。
あなたが次にお金を使うとき、その支出は「未来をつくる投資」なのか、「その場しのぎの無駄遣い」なのか――ぜひ一度、自問してみてください。
