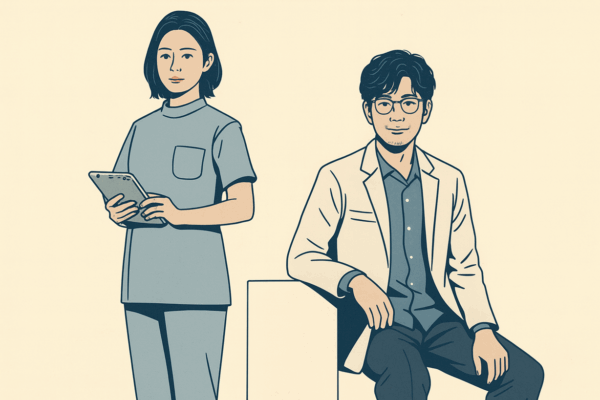
「あなたの話を聞かせてください。」
松本潤さん演じる主人公医師のこのセリフが、ドラマ『19番目のカルテ』では印象的でした。
先日最終回を迎えましたが、単なる医療ドラマではなく「総合診療科」という新しい医療領域を描いた作品として、非常に興味深いものでした。
ドラマをご覧になっていない方のために、「総合診療科」とは何かを簡単に説明します(素人説明ですみません。。)。
これまでの医療は、心臓なら循環器外科、脳なら神経内科、胃なら消化器内科というように、臓器ごとに専門医が分かれていました。
専門化が進むことで治療の精度は飛躍的に高まりましたが、一方で「どの科に行けばよいのかわからない症状」「複数の持病が絡み合う高齢者」「検査では異常が出にくい不定愁訴」といった患者には対応しにくい構造も生んでいました。
総合診療科は、こうした従来の専門の狭間に取り残されがちな患者を包括的に診る役割を担います。身体的な不調に加えて、心の状態や生活環境、家族関係なども含めて診断・治療にあたるのが特徴です。日本では2018年に「基本領域の19番目」として正式に認められた、まだ歴史の浅い診療科だそうです。
つまり「19番目のカルテ」というタイトルには、「これまでの18専門領域では救えなかった課題に挑む」というメッセージが込められています。
私は、この総合診療の考え方が、企業経営にも通じるものがあると思いました。専門部門ごとに最適化しても解決できない問題に直面するのは、病院だけではありません。会社もまた、横断的に捉えなければ見えてこない課題を抱えています。
部門の専門性がもたらす「サイロ化」
ドラマでは、外科は外科、内科は内科と、それぞれの専門性の中で最善を尽くす医師たちが登場します。そんな場面で、主人公は異なる視点から意見を述べますが、「部外者が口を出すな」と反発を受ける場面が繰り返し描かれました。
企業でも同じことが起きています。営業、開発、人事、総務、経理……それぞれが専門領域の中で成果を上げようと努力しています。しかし現場で起きる課題は、多くの場合、部門横断的です。
たとえば、
「売上が伸びない」 → 営業努力だけではなく、商品企画、生産体制、人材配置、顧客対応などすべてが関係している
「離職率が高い」 → 人事制度だけでなく、マネジメントのあり方、職場文化、働き方まで関連している
病院で「どの科に行けばいいのか分からない」患者が総合診療科に来るように、企業でも「どの部門に原因があるのか特定できない」課題は少なくありません。にもかかわらず、部門の壁は厚く、部外者が意見を差し挟むと反発を受けるのです。
「バイオ」「サイコ」「ソーシャル」で会社を見る
ドラマの中で主人公は、若い医師に「バイオ」「サイコ」「ソーシャル」という3つの視点から俯瞰的に患者を診るように指導します。
・バイオ(身体的要素):目に見える症状、検査数値など
・サイコ(心理的要素):心の状態、ストレス、意欲など
・ソーシャル(社会的要素):家族、職場、地域社会との関わりなど
従来の医療は「バイオ」に偏りがちですが、患者の生活や心の状態を含めて捉えなければ、本当の意味で「治った」とはいえません。
ドラマ内でも、テレビのアナウンサーが咽頭癌を患い、一般論では手術を選択すべきだが、声がでなくなる可能性のある手術をアナウンサーとして選択すべきか否かという葛藤が描かれていました。
この考え方は企業経営にも応用できます。
・バイオ的要素:業績数値、ビジネスモデル、業務プロセス、物的資産
・サイコ的要素:組織風土、モチベーション、リーダーシップ、労働環境
・ソーシャル的要素:業界構造、競争環境、社会からの要請
経営ではつい「バイオ」、つまり売上や利益などの数値だけを注目しがちです。しかし、組織文化や社会環境を無視すれば、根本的課題解決や持続的なビジネス成長にはつながりません。
そして、顧客との関係でも同じです。「営業力を強化したい」「システムを入れて効率化したい」という顧客からの表見的な依頼を鵜呑みにするのではなく、その背景にある心理的・社会的要因にまで踏み込み、課題を解きほぐすことが求められます。
「赤字部門」の存在
ドラマでは、総合診療科が「赤字部門」として描かれていました。手術や高額検査を行わず、問診中心で時間をかける診療は、どうしても収益性が低くなります。経営的には非効率に見えるかもしれません。
しかし、その存在は他の診療科に好影響を与え、患者満足度を大きく引き上げます。単独の効率や採算だけでは測れない、組織全体としての価値があるのです。
企業にも同じような領域があります。
・管理部門(人事、総務、経理)
・けん制機能(品質管理、内部統制)
・投資的活動(ナレッジマネジメント、社会活動)
一見すると収益を生まないように見えるこれらの活動が、全体の持続的成長を支えています。
事業単位でも同様です。短期的には利益が出ていなくても、ブランド認知や市場理解に大きく貢献しているケースがあります。
「赤字だから切る」のではなく、その部門や活動が会社全体にどのような価値をもたらしているのか。総合診療科の存在意義を考えるときと同じ問いを、経営者は持つべきでしょう。
経営者こそ「総合診療医」であるべき
企業において最も総合診療的視点を持つべき存在は、やはり経営者です。部門ごとの最適化にとどまらず、全体のバランスを見て「本質的な課題は何か」を診断する。ときには非効率に見える活動も守り育てる。その姿勢が、組織の持続的な成長を支えます。
自分の会社を一度「総合診療」の視点で見直してみてください。業績数値という「バイオ」だけではなく、組織文化という「サイコ」、そして競争環境という「ソーシャル」も含めて診るのです。そうすれば、これまで部門ごとの枠組みでは見えなかった課題や可能性が浮かび上がってくるはずです。
