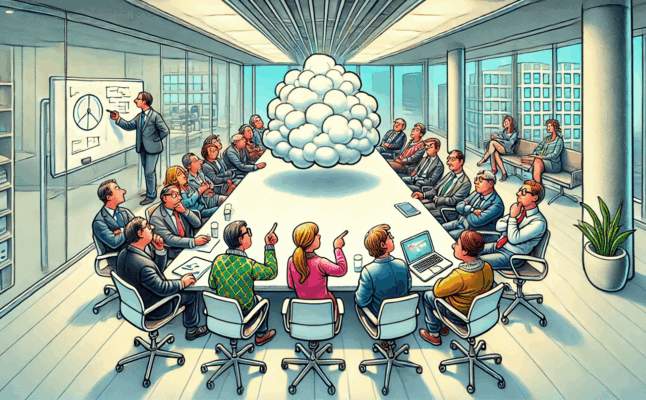
「いつになったらアウトプットが出てくるんですか?!」
「来週の会議では何を決めるんですか?!」
半ばキレ気味に質問するユーザー企業の担当者。
「大丈夫です。いつもうまくやってますから…」と答えるものの、収束点は見えず、内心は焦りまくり。
──こんな場面、経験はありませんか?
多くの場合、この原因は単純です。
サービス提供の中身が可視化されていない、からです。
なぜ顧客は怒るのか?
SIerやコンサル、広告運用、研修設計など ── 無形かつカスタムメイドの商材では、成果物が形として見えるまで時間がかかります。
ゆえに、顧客からすると「今、何をやっているのか」が分かりにくい。これが不安と不満につながります。
多くの場合、顧客はこんな状況にあります。
1. 全体ステップを説明されていない
「全体像」が理解できておらず、雲の中を歩いているような気分になる。
2. 進捗が見えない
「今どこまで来ているのか」が分からないので、プロジェクトが停滞しているように感じる。
3. 次のアクションが不明確
次回の会議で何を決めるのか、誰が何を準備するのかが分からずフラストレーションが溜まる。
4. アウトプットのイメージが湧かない
形のないサービスは、最終成果物の姿が想像しにくく、完成までの期待値が揺らぎやすい。
5. 課題が解決に向かっているのか分からない
課題が表面化したのに、それが今どんな状況なのか、誰が対応しているか分からない。
6. 誰が何をしているのか見えない
「誰が、何をどれだけやってくれたのか」が分からないので、コストに見合う価値を感じられない。
結果として、顧客は不安を抱き、時に攻撃的になります。
そしてこの「可視化不足」は、顧客満足度の低下だけに留まらず、担当者の能力についてのクレームになり、契約の破棄、契約更新拒否にも直結します。
対処方法:サービスプロセスを可視化する
解決策は、サービス提供のPDCAを見える化することです。
1. サービスプロセス全体像の可視化
・依頼から納品までの流れを図や表にする。
・例えば「要件定義 → 設計 → 実装 → テスト → 納品」の各工程と期間、アウトプット例を明示。
・顧客と最初の打ち合わせ時に共有すれば、先行きが見えやすくなる。
2. 会議ごとのテーマ明確化
・会議の目的と決定事項を事前に提示。
・「今日の会議では仕様の優先度を決定します」と宣言しておくだけで、議論がブレなくなる。
3. アウトプットの可視化・例示
・中間成果物やモックアップ、デモ版などを提示。
・完成品の一部やサンプルを早めに見せることで、最終形のイメージを共有できる。
4. 担当者ごとの進捗の可視化
・ガントチャートやダッシュボードで、担当者ごとの進行状況を共有。
・遅延やボトルネックが可視化され、早期対応が可能になる。
5. 課題の可視化
・発生している課題とその影響度、対応状況を一覧化。
・「課題はあるが対応中」「○月○日までに解決予定」と明示するだけで、顧客の心理的安心感が高まる。
そして、こうした可視化を、毎回の会議や定期進捗報告などの形で行うことです。
では、なぜやらないのか?
では、こんな大切なことどうしてやらないのでしょうか? それともできない理由があるのでしょうか?
多くの場合、「「サービスプロセス」は無形商材における「商品」の一部」であるという認識の欠如が原因です。
これには、過去の経験や職務経歴が影響していることが多い気がします。
・社内業務中心の経歴: 顧客折衝や営業をほとんど経験せず、社内調整や管理がメインだった。
・エンジニア起点マネジメント: 技術や仕様には関心があるが、顧客体験や心理的安心感には意識が向かない。
・プロダクトアウト的発想:「 モノは作ってから売るもの」という認識。モノさえ良ければ問題ないという価値観。
・ぬるま湯的顧客関係: 長年の馴れ合いや「あうんの呼吸」で成り立ってきた取引。
サービスプロセスは「商品の一部」である
こうした課題は、規模拡大を始めた小規模のサービスビジネス企業では多発します。
優秀な創業メンバーだけでやっていた時期は、その人たちの技術力や人間力で何とかなっていたが、メンバーが増えると対応が難しくなるのです。
意外なことに、程度の差はあれど、大手でも同様の現象は起こります。
中途採用のメンバーや経験の少ないマネージャーが増えることで、「勝手流」が持ち込まれてしまうのです。
しかし、サービスプロセスは商品の一部です。
だとすれば、その品質を個人の裁量に任せてはいけません。
組織として統一し、管理・改善する仕組みが不可欠です。
