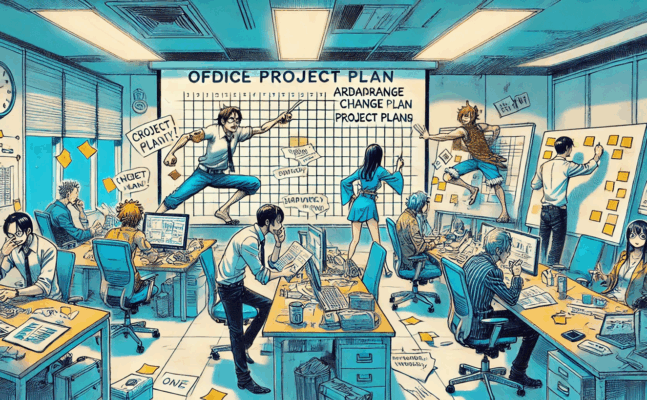
プロジェクトの現場。正式に決まったはずの内容が、気づけば「なんとなく」変わっていた――そんな経験はないでしょうか?
「当初、期限は今月末のはずだったのに、最新のスケジュール資料では来月末になっている」、「仕様書から本来盛り込むはずの機能が抜けている」、「開発メンバーが、本来の要求にない機能の開発に時間を費やしている」――ピボットとは、「大きな方向転換」というような意味ですが、こうした「勝手なピボット」は多くのプロジェクトで見られます。
さらに悪いのは、こうした「ピボット」が、現場の担当者レベルだけではなく、プロジェクト責任者やリーダーといった上位層によっても行われていることです。
なぜ 勝手に変えるのか?
プロジェクト計画を独断で変更してしまう理由は、いくつかあります。
1つは、「計画通りに進まない」からです。
プロジェクトが進行する中で、当初の見通しが外れたり、予想以上に難易度が高かったりすると、現場は「このままでは無理だ」と感じるようになります。そこで、誰かが「少しずらしてしても大丈夫」とか、「ここは省いても影響は小さい」などと、“勝手なピボット”をしてしまうのです。
もう1つは、「もっと良いアイデアが浮かんだ」からです。
進行中に、より良さそうな手法や目的が見つかることはよくあります。たとえば、計画時には不十分だったAIの能力が向上し実用できそうとか、当初のパートナー企業より技術力のあるベンダーが見つかったなどです。計画があまりうまくいっていない時は特に、白馬の王子が現れたような感覚になるものです。
最後は、「状況が変わった」からです。
最初は「コスト削減」を目的にしていたプロジェクトだったが、全社の売上低迷という状況を受けて、プロジェクト責任者が「売上アップ」を言い出した――といったようなケースです。会社や社長が背景にいるだけに、メンバーレベルでは抗しがたい変更といえるでしょう。
どれも“前向きな変更”のように見えますが、問題は、その変更が正式な合意や検証プロセスを経ていないことです。
勝手なピボットの深刻なデメリット
こうした独断的な変更には、いくつかの深刻な問題があります。
まず、「元の計画の良し悪しが評価できなくなる」という点です。
計画通りに進めていれば得られたはずの結果や課題が見えなくなり、結果として「なぜうまくいかなかったのか」が不明確になります。
また、「計画がだらだらと変わることで、もともとの目的や全体像が曖昧になる」という弊害もあります。
これは特にプロジェクトが長期に及ぶ場合に顕著です。気がつけば、「そもそも何のためのプロジェクトだったのか?」という最悪の状態になってしまいます。
中でも、「プロジェクト全体の整合性が崩れる」という問題は深刻です。
たとえば、ある工程の期間を延ばせば、他の工程とのリソース調整が必要になりますし、仕様を変えればテスト設計やユーザー教育の準備もやり直しになります。一部を変えるだけでも、全体に波及する影響は小さくありません。
こうした行動が横行すると、「いわゆるPDCAが回らなくなります」。
計画(Plan)に対する実行(Do)、評価(Check)、改善(Act)のサイクルが成り立たず、場当たり的な対応ばかりが繰り返されることになります。
正しいピボットの在り方とは
プロジェクトが計画通りに進むことはほぼありません。したがって、環境変化や新しい知見に応じて柔軟に変更を加えるのは、プロジェクトマネジメントにおいて重要な要素です。
問題なのは「勝手に変える」ことです。
したがって、計画を変更する際は、次のようなステップを踏み、勝手な変更を許容しないことが重要です。
- 現行計画がうまくいかない原因を分析する
- 修正で対応できるかを検討する
- それでも難しい場合は、大きな変更の必要性を判断する
- 複数の代替案を出して検討し、関係者の合意を得て変更の方向を決定する
このプロセスを丁寧に踏むことで、計画の質とチームの納得感、さらには最終成果の安定性が大きく向上します。
計画は“契約”である
計画とは、プロジェクトチーム全体が「こう進める」と合意した、いわば「契約」のようなものです。責任者やリーダーだからといって、それを勝手に変更してよいというものではありません。
むしろ、プロジェクトの中で最も計画を尊重する姿勢を見せるべきなのは、リーダーや責任者です。その姿勢があるからこそ、メンバーも安心して動けますし、仮に変更が必要になった際にも、筋の通った議論が行えるようになります。
そのためには、変更の手順や基準を、あらかじめ計画時に明確に定めておくことが重要です。
たとえば、「このレベルや範囲の変更は、プロジェクトオーナーと関係部門との合意が必要」といったルールを明文化しておくだけでも、無用な混乱を防ぐことができます。
人はどうしても「楽な方」「目先の良さそうな方」へと流れてしまうものです。だからこそ、計画を“守る文化”をチームに根づかせることが、プロジェクトの成功には欠かせません。
「何を当たり前のことを!」と思われるかもしれませんが、こうしたことは予想以上に相当頻繁に起きているはずです。ご自身のプロジェクトがこういう状況になっていないか、再度チェックすることをおすすめします。
