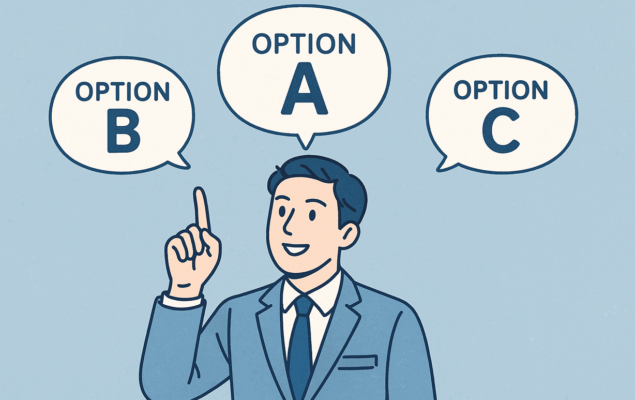
ChatGPTをはじめとする生成AIの進化により、これまで難しいとされてきた“非定型業務”の自動化が現実味を帯び、多くの企業がAIによる生産性革命に期待を寄せています。
しかし実際の現場ではどうでしょうか。すでにペーパーレス化やツール導入が進んでいる企業にとって、AIを導入したからといって劇的に生産性が上がるとは限りません。むしろ「思ったほど効果が出ないのでは」という声も少なくないのが実情です。
今回は、こうした現実をふまえ、AIの前に見直すべき「本質的な非効率の原因」について掘り下げてみたいと思います。
非効率の本当の原因は“前線”にある
業務の非効率さの原因として、人的リソースの不足やツールの未整備が挙げられることがよくあります。しかし、実際のボトルネックはそこではありません。最も大きな要因は、「イレギュラー対応の多さ」や「処理パターンの複雑さ」にあります。
そして、そのイレギュラーの多くは、営業段階で受け入れた”顧客要望”に起因しています。つまり、「自社の能力を上回る要望」や「毎回異なる仕様」が、後方業務*に「複雑性」として跳ね返ってきているのです。
*(本稿では、事務処理・生産・物流などの部門を総称して「後方」と呼びます。)
いくら社内の業務プロセスをIT化しても、受注する仕事が毎回バラバラであれば、後方は標準処理で対応できず、結果的に属人的かつ非効率な運用にならざるを得ません。AIで会議の議事録が自動で生成されたとしも、イレギュラー対応を話し合う会議自体がなくなるわけではないからです。
キモは営業段階での整理と選別
後方業務の効率化は、実は営業段階の対応次第で大きく変わります。
代表的な手段として、以下の2つが挙げられます。解決策としてはシンプルですが、実行には組織的な取り組みが求められます。
① 標準化・メニュー化
営業が受ける案件をあらかじめ標準メニューとして文書化し、それ以外の対応は原則として行わないようにします。
- 取引条件(納期、支払方法、返品条件など)をパターン化し、「Aプラン・Bプラン・Cプラン」のようにメニュー化する
- 契約書は自社フォーマットを基本とし、相手方フォーマットでの契約は例外扱いにする
- サービス内容に明確な線引きを設け、「〇〇は対応しない」「〇〇はここまで」と定義する
あるBtoBの業務支援サービス企業では、顧客ごとにカスタマイズしていたサービス提供を、3つの基本プランに限定したことで、営業とバックオフィスの連携が格段にスムーズになり、契約から実行までのリードタイムが半分以下に短縮されたという事例もあります。
また、多くのプランを用意しつつも、標準プラン以外は割高になるように価格設計することで、自然と基本プランに誘導する方法もあります。
② 苦手な領域はやらない(特化)
もう一つの方法は、自社にとってトラブルが起きやすい領域、または苦手な領域をあえてサービス対象から外すという判断です。
たとえば、システム開発会社で「開発工程での仕様変更対応」がトラブルの元となっている場合、開発そのものをやめて「運用・保守」に特化するという選択肢があります。または、「アプリ開発は行わず、AWSなどの基盤構築に特化する」といった、自社の得意分野に絞る戦略も考えられます。
このような特化戦略は、一見すると顧客対応の幅を狭めるように思えますが、対応範囲を明確にすることで品質の安定化や工数の予測がしやすくなり、結果として顧客満足度の向上につながるケースも多く見られます。
自社が担わない領域を得意とする他社と連携することで補完も可能です。
ニーズの多様化とどう折り合いをつけるか?
「標準化」や「特化」という方針に対して、「多様なニーズに応えられなくなるのでは」「時代に逆行している」といった批判もあるでしょう。
しかし、それは本当に“顧客が望んでいるもの”なのでしょうか?
多くの場合、もともとはシンプルだったビジネスが、顧客対応や個別要望への積み重ねによって複雑化していきます。そして、その複雑性に後方体制が対応しきれず、属人的な運用やトラブルが増加してしまうという悪循環に陥ります。
しかし、標準メニューを提示されれば、その範囲内でニーズを満たせるケースも実は少なくないのではないでしょうか。顧客からすれば、標準仕様を提示されなかったから、自社の要望を伝えたまでというケースもあるでしょう。
逆に、カスタマイズ対応を自社の強みにしたいのであれば、営業から後方業務までを一貫して設計し、「カスタマイズが標準」という状態にもっていくことが必要です。
営業が、効率化の起点
本稿でお伝えしたいのは、「営業部門が悪い」ということではありません。重要なのは、「フロント(営業)とバック(後方業務)の一貫性」です。
営業が「どのような要望や仕様を受け入れて良いのか」を判断できるように整理し、イレギュラーや複雑な案件を極力減らすこと。これこそが後方業務をスリムに保ち、業務全体の生産性を高めるための鍵となります。
効率化のカギは、後方ではなく「前線の設計」にあります。
