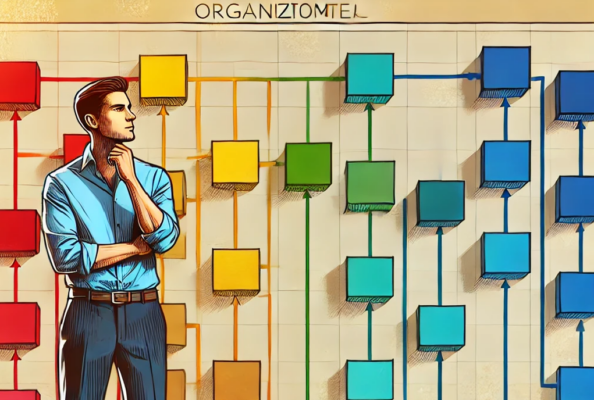
年末になり、3月決算の会社では来期の予算作成が佳境に入ってきているのではないでしょうか? 日本の企業では、予算は各部門で作成し、それを積み上げるのが一般的です。しかし、そこには問題があります。予算は、現状の組織を前提に組まれます。さらには組織自体の維持のための様々な計画が盛り込まれるのです。組織は自己保存の本能を持っている不思議な生き物であり、時に会社全体を殺すものでもあります。
今回は、そもそも組織って何? という話を書いてみたいと思います。(※ここでの「組織」は「業務機能」「部門」「職制(階層)」の総称を指します。)
組織とは「アウトプット」を出すための、良く言えば手段、悪く言えば必要悪 です。
アウトプットとは、企業で言えば顧客に商品やサービスを提供すること、そして収益を上げることです。組織はアウトプットを生むために必要なものであり、逆に言えばアウトプットに寄与しない組織は「不要」なのです。
組織はどう生まれるのか、オーダーメイドの洋服屋の例を使って考えてみましょう。
業務の流れは、例えば 営業・集客=>受注=>生地等の調達=>生産=>引き渡し=>請求=>入金 といったものです。
当初は、腕の良いテーラーである社長がこの流れをひとりでこなすところから商売を始めます。評判が良く徐々にお客が増えますが、業務が回らなくなってきて人を雇う必要に迫られます。社長は「自分と同じように、服も縫えて営業もできる人」を探しますが、そんな万能な人材はなかなか見つかりません。そこで、営業だけできる人を雇い、自分は生産に集中することにします。やがて、その営業担当者が次々と新しい仕事を開拓し、生産が間に合わなくなり生産要員を追加で雇います。更に、商売の拡大に伴う請求や支払いに増加に対応するため経理担当者を雇い、従業員が増えたのでそれを管理する人事担当者も必要となり。。。。。と、機能分担が進み、部門が増え、組織が大きくなっていく訳です。
お客様への一貫性を持ったサービス提供という観点では、営業から入金まで一人の担当者が責任をもって関わるのが理想でしょう。すべてを同一人物がコントロールできるからです。しかし、現実には以下の様な理由で組織として分業することが必要になります。
効率性追求
・得意・不得意、知識や技術などの専門性を考慮して分業
・同じ業務を大量に行うことによる習熟効果を狙う
牽制機能
・ミスや不正を防止するための第三者によるチェックする役割
管理・統制機能
・複数の作業者に適宜指示を出したり、作業を監督する役割
・機能間・部門間の調整や業務整合性を担保する役割
しかし、ビジネス環境が変われば、求められるアウトプットが変わります。これまでの仕事のやり方も変わるべきであり、よって組織のあり方も見直さなければなりません。インターネットの発展により、物理的な営業担当者はもう不要かもしれません。お客様のニーズ変化により異なるサービスが求めらているでしょう。AIの進化により事務業務は圧倒的に削減できるかもしれません。
組織が変われないということは、言い換えれば、環境変化についていけていないということなのです。組織の維持が会社の変化を阻害しているということです。既存の組織を一度忘れて、アウトプットベースでゼロから組織の要否を議論することは極めて重要です。
